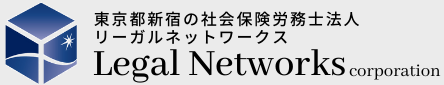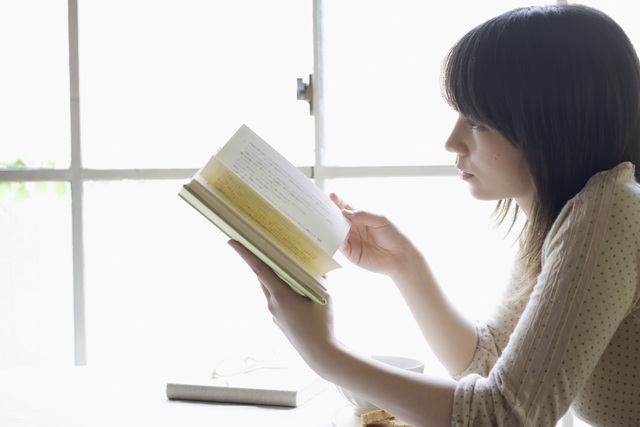スタッフブログ(労務管理ニュース)
解雇特区で得する労働者は? №39
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は以前にもご紹介した『解雇特区』について自分とは違う発想の記事がありましたのでご紹介したいと思います。
○労働者保護が優先される日本の解雇
まず最初に、現行の「解雇ルール」を確認しておきましょう。根拠は、労働契約法16条にあります。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。
実際に解雇するときは、30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う、もしくは労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けなけばならない、といったことが決められています。
整理解雇の場合も「人員整理の必要性」「解雇回避努力」「人選の合理性」「従業員に対する説明協議」の4要件が求められます。
日本の解雇を巡る条件は労働者保護が優先されているため、企業にとっては厳しいものとなっています。しかも、法律に具体的な言及がなされていないので、裁判で争われるケースが多いのが現状です。このことも企業にとってはマイナスでしょう。
○「解雇特区」はプロフェッショナルに朗報
このように見ていくと、今回の「解雇特区」は労働者に不利に思われます。では、どのような人にメリットがあるのでしょうか?「その道のプロフェッショナルを自認する人」や「企業に縛られて働きたくないと考える人」「さまざまな企業を渡り歩き、学びを深めたい人」などには都合の良い制度かもしれません。解雇要件が明確になることで、今までスペシャリストでありながら会社から評価されてこなかったような人にスポットが当たると考えています。
つまり、仕事で成果を上げられない人は会社にいれなくなり、その分の人件費が浮いて結果としてスペシャリストが待遇面でも優遇される、といった具合です。また、この制度であればプロジェクト単位で契約することができるため、複数企業からオファーを受けるスペシャリストも出てくるでしょう。
未だ不明な点も多々ある「解雇特区」ですが、自己投資を惜しまず、スキルの向上を怠らない労働者にとっては、大きなメリットになる可能性を秘めた制度といえます。
私は、解雇特区は労働者に不利になるのではないかとばかり思っていましたが
人によってはプラスになる可能性もあるんですね。
http://getnews.jp/archives/432201
平成25年10月11日
日雇い派遣、禁止後1年で「解禁」提案なぜ? №38
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は労働者派遣について「ある提案」がでているそうなのでご紹介したいと思います。
10月4日、政府の規制改革会議は「日雇い派遣」を解禁するよう求める意見書をまとめました。しかし、日雇い派遣といえば昨年禁止されたばかりです。なぜ、あらためて解禁が議論されているのでしょうか。
日雇い派遣は、労働者と派遣元の契約が30日以内である短期の派遣のこと。
仕事があるときだけ派遣会社と雇用契約を結ぶ「登録型」の派遣です。
派遣元に常時雇用され、仕事の有無にかかわらず給料が支払われる「常用型」の派遣に比べると、不安定な雇用形態とされています。
労働者保護の観点から、2012年10月の労働者派遣法改正で原則禁止となりました。
解禁へ向けての議論が始まった背景には、規制緩和を通じて経済成長を進めようとする「アベノミクス」があります。つまり「働き方の選択肢」を増やせば、それだけ新たな就業機会も生まれるとの考えです。
日雇い派遣解禁は、働き方の選択肢が増える一方で、再び雇用の不安定化を助長しかねないとの懸念もあり、波紋を呼びそうです。
アベノミクスがはじまってから禁止された事が緩和されているような気がします。
緩和されることによっていい方向にむいていけばいいのですが。。。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131010-00000002-wordleaf-bus_all
平成25年10月10月
高額療養費制度を見直しへ 高所得者の上限額引上げ №37
こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。
今日、出勤しているときにキンモクセイの香りが
どこからか漂ってきて秋を感じました。
さて本日は高額療養費制度のニュースをご紹介したいと思います。
厚生労働省は9日、医療費の自己負担が上限額を超えた分を払い戻す高額療養費制度を見直す方針を示した。70歳未満と70〜74歳の世代で、所得の高い人の月々の上限額を引き上げ、負担を増やす。上限額の目安となる所得の区分をより細かくして、所得に応じた負担を徹底する。2014年度以降の実施を目指す。
きめ細かい仕組みに切り替えるのは、制度の持続を脅かす給付の膨張に歯止めをかけるためだ。政府の社会保障制度改革国民会議は8月にまとめた報告書で、70〜74歳の医療費の窓口負担を2割に上げる方針とともに、高額療養費の負担上限額の見直しを盛り込んだ。
厚労省は9日の社会保障審議会医療保険部会に具体案を示した。年内をメドに上限の引き上げ額や所得区分の数を詰める。部会には自営業者などが加入する国民健康保険(国保)の保険料でも高所得者を念頭に、上限額を上げる方針を示した。
高額療養費の負担を見直す対象は、70歳未満の世代と70〜74歳の世代に分かれる。両世代でかかる高額療養費は、全体の年間の払戻額の約2兆円の8割近くを占める。国民会議が示した「能力に応じて応分の負担を求める」考えに基づき、高所得者への負担を重くする。厚労省は医療費の自己負担増や大病院の外来受診の定額自己負担などと合わせて、抑制策に踏み込む方針だ。
高額療養費の負担上限額は現在、70歳未満の高所得者(夫婦の年収で790万円以上)の場合、1カ月で約15万円。これに次ぐ所得者層(210万円以上790万円未満)で約8万円だ。
見直し案によると、基準となる所得区分をそれぞれの世代で細分化し、所得の多い人の区分で上限額を引き上げる。
区分の数は未定だが、70歳未満では高所得者を3つ以上に分ける案が浮上している。そのすべてで負担の上限額を現行から上げる。高所得者に続く一般層も3つ程度に分け、最も高い区分は上限額を上げる。70〜74歳でも現役並み所得者と一般層とを2つずつに分け、上の区分で上限額を引き上げる方向だ。
一方、低所得者は上限額を変えないほか、細かくした区分でも下のほうは据え置く。70歳未満の一般層では、低所得者寄りの区分では逆に上限額を引き下げる。金額や区分によっては財政の負担が膨らみかねない。
厚労省は新しい制度の導入時期について、政府が14年度から適用を目指す70〜74歳の医療費の負担引き上げを正式に決めた後に、タイミングを見定めるとしている。見直しに伴い必要なシステムの改修には、年単位の時間がかかるともいわれ、実施は早くて14年度後半以降になる見込みだ。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0903S_Z00C13A9EE8000/
平成25年10月9日
政府が来年度から中小企業の育休支援拡大へ №36
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今年も残りあと3か月となりました。
そろそろ年調の準備を始めていかなければいけません。
年末は忙しくなるので、早め早めに準備していきたいですね。
今日は働く女性に嬉しいニュースを見つけましたのでご紹介したいと思います。
政府は、中小企業の従業員が育児休業を取得しやすくするため、来年度予算の概算要求に関連事項を盛り込む。
育休取得や職場復帰に関する社内制度づくりをサポートする「育休復帰プランナー」を来秋から全国に配置。
また、従業員が育休を取得した企業には1社あたり最大60万円を助成する考え。
育休を習得しやすくなることによって少しでも職場環境がよくなり、
女性が出産してからも仕事を継続しやすくなるのはいいことですね。
平成25年10月8日
企業を優先「解雇特区」 №35
こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は安倍政権が構想する従業員を解雇しやすくしたり、
労働時間の規制をなくしたりする特区のことについてご紹介したいと思います。
特区をつくるねらいは何か?働き手にどんな影響があるのでしょうか?
「解雇特区」とは
○ベンチャー・外資の進出促す
特区は安倍政権がかかげる成長戦略の柱の一つ。
企業に「不便」な規制をゆるめ、もうけやすい環境を整える。
政府は5月、国家戦略特区ワーキンググループ(WG)をつくり、自治体や企業にも提案を募って、雇用や医療、農業、教育などの特区を検討してきた。
うち雇用では、
(1)入社時に結んだ条件に沿えば解雇できる
(2)一定の年収があれば労働時間を規制しない
(3)有期契約で5年超働いても、無期契約になれるルールを適用しなくていい
の3点だ。働き手を守る労働契約法や労働基準法に特例を認める。
(1)と(2)の特例は、開業後5年以内の企業の事業所に適用。
外国人労働者の比率が3割以上の事業所では(3)の特例も使える。ベンチャーの起業や、海外企業の進出を促すためだという。
背景にあるのが、「いまの解雇のルールがわかりにくい」という考えだ。
いまは、やむを得ない事情がないと、企業は自由に解雇できない。解雇は働き手にとって不利益が大きいためだ。
裁判で解雇の是非を争うと、裁判所の総合的な判断にゆだねられる。
○「遅刻したら解雇」も可能に
一方、特区では、企業と働き手があらかじめ結んだ約束を優先させる。
例えば「遅刻をすれば解雇」と約束し、実際に遅刻したら解雇できる。解雇のルールを明確にすれば、新産業の育成や海外企業の活動がすすむという考えからだ。
だが、強い立場の企業が、弱い労働者に不利な条件を強要して雇用が不安定になるおそれがある。
近年、解雇などが原因の労働紛争が増え労働問題は複雑になっています。
その中で解雇をしやすくしてしまうとさらに労働トラブルが増えてしまいそうで心配ではあります。
http://www.asahi.com/politics/update/0930/TKY201309300004.html
平成25年10月7日
保険証リーダー №34
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は「こんな便利な物があったのか!」と驚いた物があったので
ご紹介させていただきます。
保険証リーダーという物で
医療事務システムなどに健康保険証の読み取り機能を追加するためのツールウェア。
印刷や保存状態によって肉眼でも読み取りにくい保険証もあり、システムへの入力や確認用コピー保存に労力が必要であったが、わずか数工程のシステム改変で誰でも簡単にペーパーレスで登録作業が行えるそうです。
社労士事務所でもクライアントの保険証を管理するので、
これは社労士事務所で導入してもかなり使えそうだなっと思いました。
http://www.zaikei.co.jp/releases/127680/
平成25年10月3日
ATM手数料値上げへ=来年4月、108円に—消費増税 №33
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
最近、秋雨前線や台風で天気の悪い日が続いています。
週末くらいは晴れてほしいですね。
10月1日に安倍首相から来年4月に消費税率を8%に引き上げると表明がありました。
今日はそのことに関連した話題をご紹介したいと思います。
消費税率の8%への引き上げを閣議決定したのを受けて、金融機関の現金自動預払機(ATM)の手数料も2014年4月に引き上げられる見通しです。
金融界は自行預金者から徴収する利用手数料(平日夜間・休日)を、現行より3円高い1回当たり108円に引き上げる方向で検討に入ったようです。
金融庁は消費税率引き上げに伴い、手数料の上限を事実上定めた関連法令の改正に着手して、預け入れ、引き出し金額が1万円以下で105円、1万円超では210円となっている現在の上限は、それぞれ108円、216円になる見込みです。
消費税が上がることによってATMの手数料も上がってしまうなんて
私はとても意外でした。ATMの手数料はかなり身近なだけにショックです。
一緒に預金の利率も上がると嬉しいのですが。。。
平成25年10月2日
裁量労働制、拡大へ議論=1年めどに結論 №32
こんばんは
リーガルネットワークスの大川です。
本日はあまり時間がなく、気になったニュースを添付だけさせて頂きます。
厚生労働省は27日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会を開き、労働時間と無関係に一定の賃金が支払われる「裁量労働制」の拡大に向けて議論を始めた。1年をめどに結論を出し、労働基準法の改正案を国会に提出する方針。
裁量労働制は、仕事の進め方などを従業員の裁量に委ね、あらかじめ決めた時間を働いたとみなす制度。ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の促進に加え、先進国でも低位にとどまる労働生産性を向上させるのが狙いだ。ただ、低賃金での長時間労働が拡大しかねないと、警戒する声も少なくない。
厚労省は経営企画や財務などの従業員に適用される「企画業務型」の裁量労働制に関し、対象などを広げたい考え。また、始業・終業時間を柔軟にするフレックスタイム制の拡大も検討する。
Yahoo ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130927-00000213-jij-pol
平成25年10月1日
お問合せはこちら
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
03-6709-8044
このページのトップに戻る
イチオシ情報
池袋事務所よりお知らせ
最新情報
2025年12月29日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2026年1月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
2025年12月1日
誠に勝手ながら、下記の日程を年末年始休業とさせていただきます。
2025/12/27~2026/1/4
人材募集
無料個別相談 実施中!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
お問合せはこちら
事務所概要

社会保険労務士法人
リーガルネットワークス
03-6709-8044
代表社員:勝山 竜矢
代表プロフィール
住所・アクセス
◆本部・新宿御苑事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」
徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」 徒歩6分
◆池袋事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8044
各路線「池袋」C6出口
徒歩6分
有楽町線副都心線「要町駅」 徒歩10分
業務エリア
池袋・新宿・渋谷・品川など
東京23区を中心に対応
事務所概要はこちら
アクセスマップはこちら
免責事項
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。