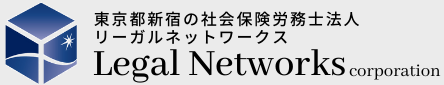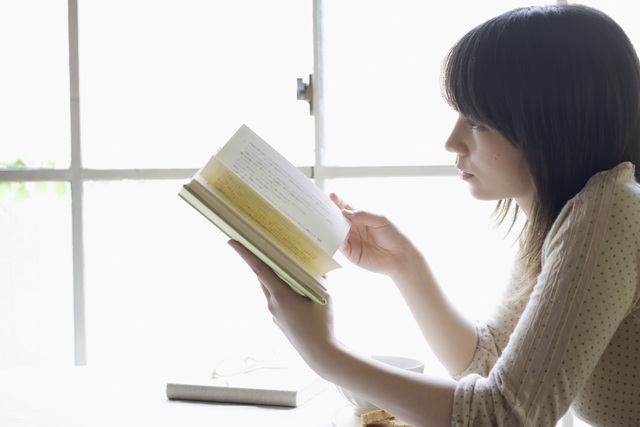スタッフブログ(労務管理ニュース)
労働安全衛生規則 健康診断2 №55
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は、昨日に引き続き、労働安全衛生規則の健康診断についてご紹介したいと思います。
定期健康診断は常時労働者を雇っている場合に毎年発生するのでしっかり内容を把握しておかなければなりません。
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)貧血検査
(7)肝機能検査
(8)血中脂質検査
(9)血糖検査
(10)尿検査
(11)心電図検査
※常時使用する労働者
パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成19年10月1日基発第1001016号通達で示されています。その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。
参考資料 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0907-4i.pdf
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q16.html
場合によっては省力できる項目もありますので、上記のリンクからご確認下さい。
最近では、若い年齢の方でも生活習慣病などにかかる傾向にありますので、年齢関係なく、毎年きっちり健康診断をすることによって健康管理ができ、健康な身体で働くことによって仕事の効率も上がると思います。それに健康を意識することでメタボ防止にもなりますね。健康診断は大事な福利厚生です。
平成25年11月8日
労働安全衛生規則 健康診断 №54
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
最近、カラっと晴れる日が少ないですね。
毎年この時期は地味に天気が悪い日が続く気がします。
今日は労働安全衛生規則の健康診断の部分についてご紹介したいと思います。
○雇入時の健康診断
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査
(5)血圧の測定
(6)血色素量及び赤血球数の検査
(7)血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(ガンマ—GTP)の検査
(8)低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
(9)血糖検査
(10)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(11)心電図検査
雇入時の健康診断項目、参考にして頂ければ幸いです。
平成25年11月7日
即時解雇 №53
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は、昨日少し触れました即時解雇についてご紹介したいと思います。
よくドラマなどで「クビだー」と言って労働者を解雇している場面があります。
実は、解雇予告手当を払わずに、労働者を即時に解雇できるのは、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合にできるんです。
認定を受ければ、解雇の効力は認定を受けた日ではなく解雇の意思表示をした日に発生します。
ただし、労働基準監督署長の認定を受けなくても、認定申請を行わなかった20条違反による刑事上の問題はあるものの、民事的には認定を受けるだけの事由があれば即時解雇は有効で解雇予告手当の支払は不要というのが判例の傾向であります。(でも認定はきちんと受けましょう)
労働基準監督署長の認定を受けることができるのは以下の事由です。
・天災事変その他やむ得ない事由。
・労働者の責に帰すべき事由(一般的には「懲戒解雇」事由に属するものに相当し、「普通解雇」には属さない)
やはり、できるだけ即時解雇という手段は使わずに退職手続きを行ないたいですね。
労働紛争になる原因となってしまいますので。。。
平成25年11月6日
諭旨解雇 №52
今日は、最近話題になりました、諭旨解雇についてご紹介したいと思います。
諭旨解雇(ゆしかいこ)は、懲戒処分の一形態としての解雇です。
解雇には懲戒解雇、普通解雇、整理解雇等の区別がありますが、懲戒解雇が最大の懲戒処分であるのに対し、それよりも若干処分を軽くしたものが諭旨解雇です。
諭旨解雇に法律上の定義はありません。通常、懲戒解雇(即時解雇)が即日、予告手当なし、退職金不支給に対し、若干緩やかな条件となります。
しかし、解雇が自己都合退職より経済面で処遇がよくなることが多く制裁の意味をなさないため、諭旨解雇ではなく本人が自発的に行う諭旨退職にすることが多いようです。
懲戒解雇に相当する事実が発覚しても最後まで冷静に判断することが大事だと思います。
又、事前に就業規則などをきちんと整えておくと有効です。
平成25年11月5日
健康保険被扶養者4 №51
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
前回に引き続き、健康保険被扶養者についてご案内したいと思います。
留意事項
(1)婚姻を契機として配偶者を扶養に入れる場合などで、住所が変わるときは、同時に被保険者住所変更届の提出が必要です。
(2)被扶養配偶者が、20歳以上60歳未満で国民年金の被保険者である場合は、3枚目の国民年金第3号被保険者該当届を同時に提出してください。
(3)国民年金第3号被保険者該当届を提出する場合で、同時に氏名変更を届出される場合は、年金手帳(第3号被保険者となる方のもの)を添付してください。
(4)住民票や戸籍謄(抄)本は、直近の状態を確認します。そのため、提出日から遡って60日以内に発行されたものを提出してください。
(要チェック)
(5)被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上遡及する場合は、被扶養者の氏名、生年月日、続柄、被扶養者になった日、収入要件確認のための書類など、事実を確認できる書類を添付してください。
(6)後期高齢者医療制度の被保険者は、協会けんぽの被扶養者にはなれませんので、ご注意ください。
以上、健康保険被扶養者のご案内でした。
扶養を追加するだけでも、様々な要件などがあります。
意外と扶養の範囲はどこまでいけるのか?など正確に把握できてないことがあります。
ですので、これからもっと労働・社会保険の書類の提出方法などをご案内していけたらなと思います。
平成25年11月1日
健康保険被扶養者3 №50
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は、昨日までご案内していた健康保険被扶養者を追加、削除したりする場合の提出書類・添付書類などをご案内したいと思います。
まず健康保険被扶養者(異動)届が届出書類となります。
次に添付書類です。
<1>は全員、添付が必要です。
<2>〜<4>は、該当する場合のみ、添付が必要です。
<1>収入要件確認のための書類
○被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れることになります。その際は、被扶養者(異動)届(削除)の手続きが必要になります。
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
事業主の証明があれば添付書類は不要。
ただし、被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意下さい。
(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
「雇用保険受給資格者証の写し」
(ウ)年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」
(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
直近の確定申告書の写し
(オ)上記イ〜エ以外に他の収入がある場合
上記「イ〜エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」
(カ)上記ア〜オ以外
「課税(非課税)証明書」
(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。
<2>続柄確認のための書類
○被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。
「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など
ただし、下記<3>に該当する被扶養者で、添付された被保険者世帯全員の住民票(コピー不可)により続柄が確認できる場合を除きます。
<3>続柄確認のための書類
○被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となります。
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可)」
<4>内縁関係を確認するための書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可)」など
以上が添付書類となります。
つづく
平成25年10月30日
健康保険被扶養者2 №49
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
昨日に引き続き健康保険被扶養者の範囲についてご案内したいと思います。
(1)収入要件
年間収入※130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付・公的年金・健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますの で、ご注意下さい。
(※) 収入が被保険者の収入の半分以上の場合であっても、被保険者の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
つづく
健康保険被扶養者 №48
こんにちは
リーガルネットワークスの大川です。
今日は健康保険被扶養者の範囲についてご案内したいと思います。
(1)被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくても事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
わかりやすく説明すると配偶者・子、孫および弟妹・父母、祖父母などの直系尊属は被保険者と同居している必要がありません。
(2)被保険者同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
1.被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
2.被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
3.2の配偶者が亡くなった後における父母および子
つづく
平成25年10月28日
お問合せはこちら
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
03-6709-8044
このページのトップに戻る
イチオシ情報
池袋事務所よりお知らせ
最新情報
2025年12月29日
弊社クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています。
最新の2026年1月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!
2025年12月1日
誠に勝手ながら、下記の日程を年末年始休業とさせていただきます。
2025/12/27~2026/1/4
人材募集
無料個別相談 実施中!
まずは話を聞いてみたいという企業様。
代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。
企業様向けに約60分の個別相談が無料です。弊社もしくは貴社へお伺い致します。
お問合せはこちら
事務所概要

社会保険労務士法人
リーガルネットワークス
03-6709-8044
代表社員:勝山 竜矢
代表プロフィール
住所・アクセス
◆本部・新宿御苑事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8919
丸の内線「新宿御苑前」
徒歩4分
都営新宿線「新宿三丁目駅」 徒歩6分
◆池袋事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-34-13
貝塚ビル302
電話番号:03-6709-8044
各路線「池袋」C6出口
徒歩6分
有楽町線副都心線「要町駅」 徒歩10分
業務エリア
池袋・新宿・渋谷・品川など
東京23区を中心に対応
事務所概要はこちら
アクセスマップはこちら
免責事項
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。