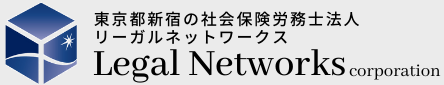裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが追加
裁量労働制とは、業務の遂行手段や時間配分等を従業員の裁量にゆだね、実際に働いた時間に関わらず、あらかじめ定めた時間を労働時間とみなす制度です。
裁量労働制には、次の2種類があります。
| 専門業務型裁量労働制 | 研究開発やデザイナー、税理士等厚生労働省令で定める19種の業務に限り導入できます。 | ||
| 企画業務型裁量労働制 | 企画、立案、調査及び分析等の業務であって、業務の性質上、使用者が具体的な指示をしない事業場で導入できます。 | ||
2024年4月1日以降、裁量労働制の導入および継続に新たな手続きが必要となります。
具体的には、下記の対応が必要になります。
対応事項(2024年4月1日以降)
| 対応が必要な事項 | 対象となる制度 | |
| ①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める ・専門業務型では、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを労使協定に定める(企画業務型にはすでに義務付け規定あり) ・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定・労使委員会の決議に定める | 専門業務型 企画業務型 | |
| ②労使委員会に賃金・評価制度を説明する ・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)を労使委員会の運営規程に定める ・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める |
企画業務型 | |
| ③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う ・制度の適正な運用の確保するため、制度の実施状況の把握の頻度・方法等を労使委員会の運用規定に定める | 企画業務型 | |
| ④労使委員会は6ヶ月ごとに1回開催する ・労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを労使委員会の運用規定に定める | 企画業務型 | |
| ⑤定期報告頻度の変更 ・労働基準監督署への定期報告の頻度について、起算が「決議の有効期間の始期」に変更となり、初回は6か月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回へ変更となる | 企画業務型 | |
こちらもご参照ください(出典:厚生労働省HP 「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」)
お問合せはこちら
中小企業の勤怠管理・給与計算に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。
社会保険労務士法人リーガルネットワークス
03-6709-8044
このページのトップに戻る